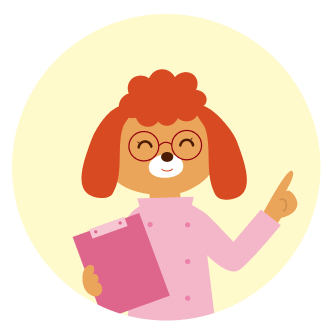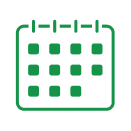発達障害とは
発達障害は、生まれつき「得意・不得意」の差が大きく、
それが原因で生きづらさがある状態
子どもの頃は気づかれにくかった
・元気が良すぎる
・勉強が苦手なだけ
・一人で過ごすことが多い
・趣味にすごく熱中する
大人になって「生きづらさ」を感じる
・人間関係のトラブルが多い
・友達が出来ない
・仕事が長続きしない
・忘れ物が多い
・衝動性が抑えられない
発達障害の種類
-
ASD(自閉スペクトラム症)
ASDとは、「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、こだわり」「感覚の異常」などの特徴をもつ障害です。
主な特性・自分の思いを伝えられない
・空気が読めない
・趣味などのこだわりが強い
・音や光が苦手 -
ADHD(注意欠如・多動症)
ADHDとは、「集中できない」「じっとしていられない」「考えるよりも先に動く(衝動的な行動)」などの特徴をもつ障害です。
主な特性・忘れ物が多い
・じっとしていられない
・活動に集中できない
・待つことが苦手 -
SLD(学習障害)
SLDとは、「字を読むことや書くこと」「算数の計算」などの学習的技能が年齢相応よりも劣っている障害です。
主な特性・字が流暢に読めない
・字が正確に書けない
・計算が出来ない
こんなお悩み、
思い当たりませんか?
このような方は、発達障害の可能性があるかもしれません。
- 空気が読めないと言われる
- 衝動買いが多く金銭管理ができない
- 整理整頓が苦手
- 衝動をコントロールできない
- 物事を予定通りに終わらせることができない
- 急な変化への対応ができない
- 仕事が覚えられない
当てはまることがいくつかあって気になる方は、ひとりで抱え込まず、
まずは当院に相談してみませんか?
小さな気づきが、これからの生きやすさに繋がる
第一歩になるかもしれません。
受診の流れ
-
01

診察
(丁寧なヒアリング)現在の困りごとはもちろん、
- 幼少期の様子
- 学生時代の友人関係・成績のこと
- 社会人の方はお仕事の経歴や退職理由 など
あなたのこれまでをゆっくり伺いながら、心の特性を見ていきます。
-
02

心理検査
(必要に応じて)診察の結果、発達障害の可能性がある場合は、心理検査を行います。
検査はほとんどが「質問に答える形式」で、痛みなどは一切ありません。 -
03

診断と今後の
ご相談診察と検査の結果をもとに、必要があれば診断を行います。
そのうえで、- あなたに合ったサポートの方法
- 今後の過ごし方や治療の方向性
などを一緒に考えていきます。
サポート内容診断後の流れ
薬物療法
治療法には薬物療法と非薬物療法があります。併用することもあります。
薬物療法は、どのような薬があるのか、その効果、副作用などを説明し、使用するのかどうか相談の上、決定します。発達障害の一つであるADHD(注意欠陥多動障害)には専用の薬がありますが、その他の発達障害には専用の薬がないため、発達障害が原因で起こる二次障害(抑うつ気分、不安、不眠など)に対して薬物療法を行います。
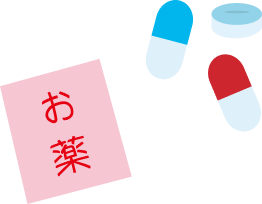
非薬物療法

カウンセリング
考え方のクセを見直す「認知行動療法」や、自分の特性を理解して相手に伝える練習などを行います。

デイケアでのグループワーク
似た悩みを持つ人と話し合い、対処法を学び合う中で「自分に合うやり方」を見つけていきます。
決まった時間に通うので、時間管理の練習にもなります。

訪問看護による個別サポート
忙しくて通院が難しい方には、訪問看護で短時間(30分ほど)の個別トレーニングも可能です。
内容はオーダーメイドで、その方の状況に合わせた効率的なサポートを行います。
繰り返しながら、少しずつ前へ
悩みは一つ解決しても、新しい壁にぶつかることもあります。
しかし、薬物療法と非薬物療法を繰り返し一歩ずつ取り組むことで「自分らしい過ごし方」が見つかっていきます。
「湯たんぽトライアル」の
ご案内
湯たんぽトライアルとは
発達特性が要因となって、日常生活&社会生活の中でいつの間にか心身に負担がかかり、血流が悪くなっている箇所やその発生要因を見つけて「湯たんぽ」で手当するイメージです。
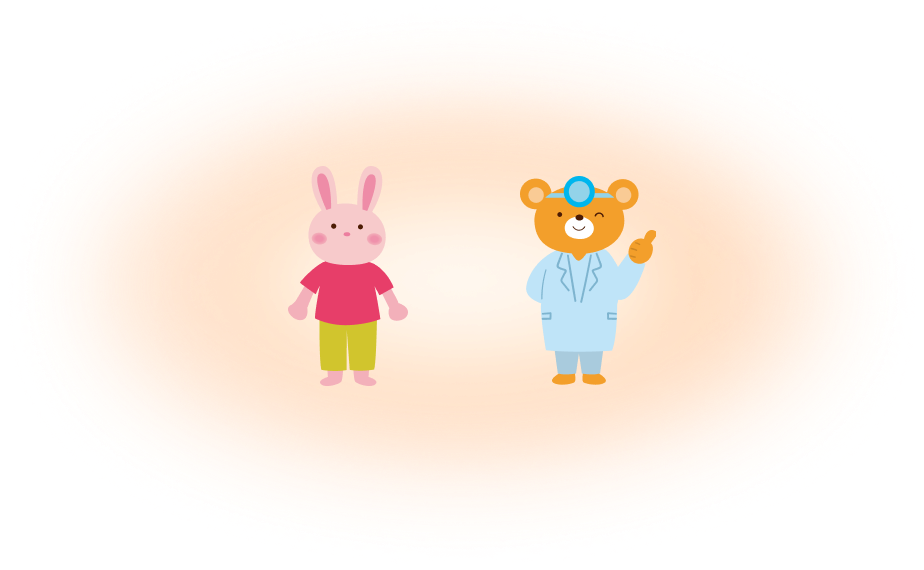
サービスの流れ
湯たんぽ回数
4回
(例えば週1回or2週に1回など)
-
STEP1

ご希望に合わせて、
スケジュールを一緒にご相談します。 -
STEP2

専門のスタッフがご自宅に
伺い、30〜40分ゆっくりと
お話をお聴きします。 -
STEP3

最終回には、これまでの
内容を一緒に振り返って
終了となります。
「湯たんぽトライアル」
ご利用方法
湯たんぽトライアルをご希望の方は、
下記いずれかの方法でお申し出ください。
- 診察時に主治医へ「湯たんぽトライアル希望」とお伝えください
- または、代表電話にお電話いただき「湯たんぽトライアル希望」とお伝えください
後日、訪問看護スタッフからお電話させていただき、その後の日程相談となります。
こんなことが
出来るようになります
出来
るようになる
相談できる
ようになる
長続きする
ようになる
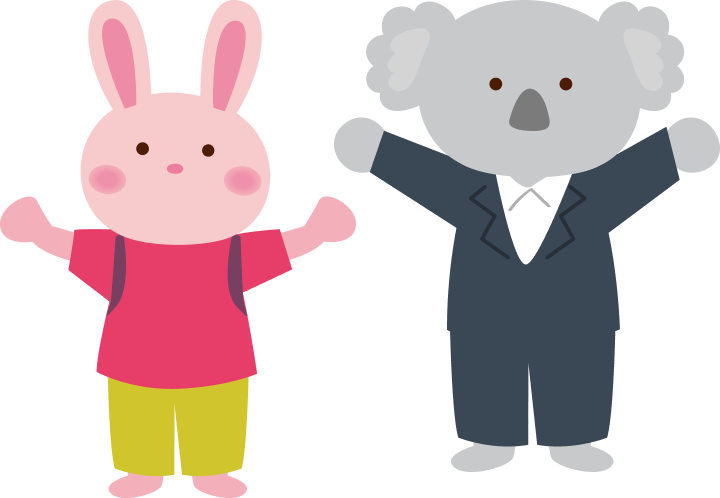
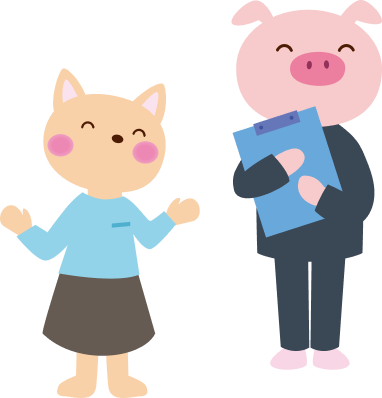
患者さんの声

20代・男性
私は平成25年頃、仕事のストレスから不眠が続き、内科を受診しました。睡眠導入剤を処方されましたが、半年以上飲み続けても改善せず、心療内科を紹介されて受診することになりました。
その頃には、気分の落ち込みや倦怠感、やる気の低下などの症状も出てきており、「うつ病」と診断され、抗うつ薬の服用が始まりました。薬の効果もあり、徐々に症状は改善し、一度は仕事に復帰できましたが、半年ほどで再び体調が悪化し、退職することになりました。
その後は、就職への不安から就職活動もできず、しばらくはボランティアや単発のアルバイトをしていましたが、どれも長続きしませんでした。うつの症状自体は、良くなったり悪くなったりを繰り返していましたが、日常生活に支障が出るほどではなかったため、いくつかの仕事を転々とする日々が続きました。
そんな中で、「なぜ仕事が長続きしないのか」を改めて振り返ったところ、
- 職場の人間関係がうまくいかない
- 残業などの予定変更が大きなストレスになる
- 仕事の説明をされても内容を覚えられない
- 優先順位がわからず、期限を守れないことが多い
といった自分の傾向に気づきました。そこで心理検査を受けた結果、「自閉スペクトラム症(ASD)」という発達障害の診断を受けました。
その後はカウンセリングを通じて、自分の特性を理解し、就職の際には職場にあらかじめ配慮をお願いしました。たとえば、
- 曖昧な表現を避けて、わかりやすく伝えてもらう
- 予定変更や残業はできるだけ避けてもらう
- 仕事の指示は口頭ではなく、マニュアルなど視覚的に示してもらう
- 業務の優先順位を上司に決めてもらう
など、具体的なサポートを受けることで、今は安定して仕事を続けられています。

30代・女性
私は30代の女性です。子どもの頃から、勉強は普通にできていましたが、友達はほとんどおらず、一人で過ごすことが多かったです。ただ、特につらい思いをしたわけではなく、不登校になることもありませんでした。
大学を卒業後は、プログラマーとして就職し、10年以上働いてきました。仕事も安定しており、大きな問題もなく、欠勤もほとんどありませんでした。
最近、インターネットで発達障害について知る機会があり、自分にも当てはまる部分があるのではと思い、受診することにしました。診察や心理検査を受けた結果、「自閉スペクトラム症(ASD)」と診断されました。
診断によって、自分にいくつかの特性があることがわかりましたが、
- 集団での行動が苦手 → 一人での作業が中心なので困っていない
- 予定の変更が苦手 → 毎日同じ業務で、残業もなく安心できる
- コミュニケーションが苦手 → 会話はほとんどメールで完結しており問題なし
- 大きな音が苦手 → 静かな職場で集中できている
というように、現在の職場環境が自分にとても合っていたため、これまで特に困ることもなく、気分の落ち込みや不安などの二次的な症状も出ていません。
現時点で困りごともなく、日常生活や仕事も安定しているため、診断後の通院は終了となりました。